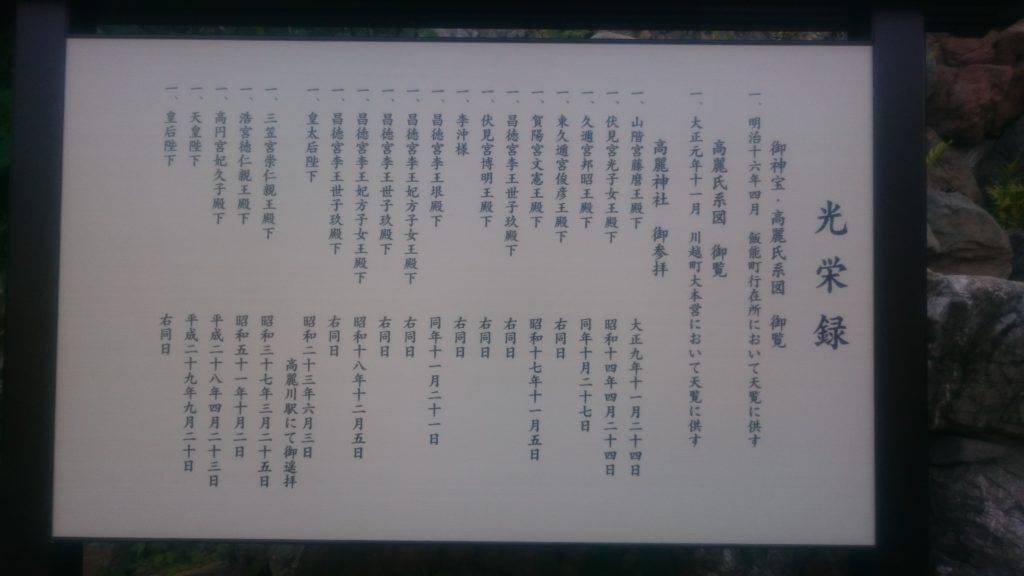視覚情報とイメージの出し入れを行うには、どうすればよいであろうか?
目を開ければ、外界の情報が勝手に目に入ってくる。
目を閉じると、外界の情報は遮断される。今、見ていた風景は、イメージするしかない。
このとき、あたかも目でみているようにイメージすることは出来ないのであろうか?これができると、カメラアイという能力をもった人たちのように、風景をカメラのように記憶しておいて、それを頭の中で見ながら、情報をアウトプットすることができる。
参考書のページをめくっている風景を記憶し、後で、その風景を頭の中でイメージする。何ページの何処に何が書いてあったのかを、そのイメージの風景を、見て、読み上げるのである。内容は、理解していない。
どうすれば、できるのであろうか?
目を開いているときは、外の情報が常に目に入り、錐体細胞によって電気信号に変換され続け、脳内で認知される。
目を閉じているときは、視覚情報は遮断され、錐体細胞の信号変換も停止する(or 黒という情報変換をし続ける)。視覚という認知機能は、「錐体細胞による光刺激の電気信号変換」なので、光が遮断された段階で視覚による認知機能はなくなる。
よって、記憶した情報、イメージした情報を、視覚的に読み上げることは不可能であると考えられる。
しかし、もし、錐体細胞から信号変換された情報を覚えていて、脳内から錐体細胞を刺激し、その刺激の脳内への反射を認知できれば、あたかもイメージを視覚的に見るという体験ができるはずである。
しかし、電気回路を思い出せば分かるように、信号は常に漏れるので、伝送ステップが多いと情報の欠落も多くなる。
つまり、外界からの光情報を目で見ているときと、イメージを目で見るときは、下図のような情報伝達経路になり、後者の方が体内での処理が多いので、情報がロスが大きいということである。太矢印は、体内処理。
【目を開いて情報を認知するときの処理経路】
情報(光) → 光による錐体細胞の刺激 ➡ 電気信号変換 ➡ 脳内検知
【イメージ情報を視覚的に認知するときの処理経路】
イメージ(電気信号) ➡ 電気信号による錐体細胞の刺激 ➡ 錐体反応の反射➡脳内検知
また、イメージは記憶であり、そんなに精度よくとどめることは出来ない。したがって、錐体細胞を刺激するには至らないのである。
ところで、ここまで話てきて、そもそも、脳内イメージから錐体細胞を刺激し、それを視覚的に認知することなどできるのか?という疑問があると思う。
結論から言うと、私はこれは可能だと思っている。なぜなら、よくネットなどで落ちている、オレンジカード( オレンジ色の中に、青い丸の描かれたカード )を30秒ほど見て目を閉じると、瞼にその像、または色の反転した像を見ることができるからである。
目でみた視覚情報が電気信号になり、短期記憶され、それが脳内から目の錐体細胞を刺激するから、目で感じられるのだと思っている。なお、この情報を10秒ほどで消えてしまう。
よって、海馬だか、内臓だか分からないが、とにかく短期記憶で外界の情報をしっかり捉えられれば、視覚的にそれを見ることは出来ると思うのである。
※ 最も、ここまで記憶でとらえることができていたら、視覚的に読み上げる必要はないと思うが。。。
では、短期記憶を鍛えるにはどうしたらよいのであろうか?
よく、短期記憶は、脳の「海馬」というところに蓄えられると言われる。情報は電気信号だから、海馬がどのように記憶をとどめるのか?を理解し、それをコントロールできればよさそうに感じる。
この点については、また今度、考えてみる。