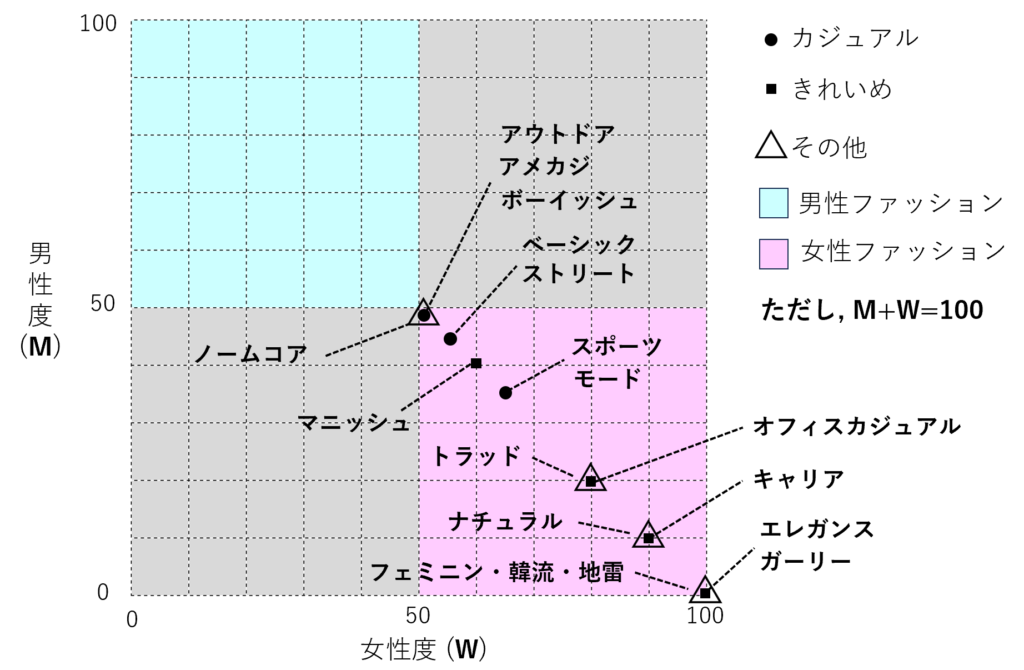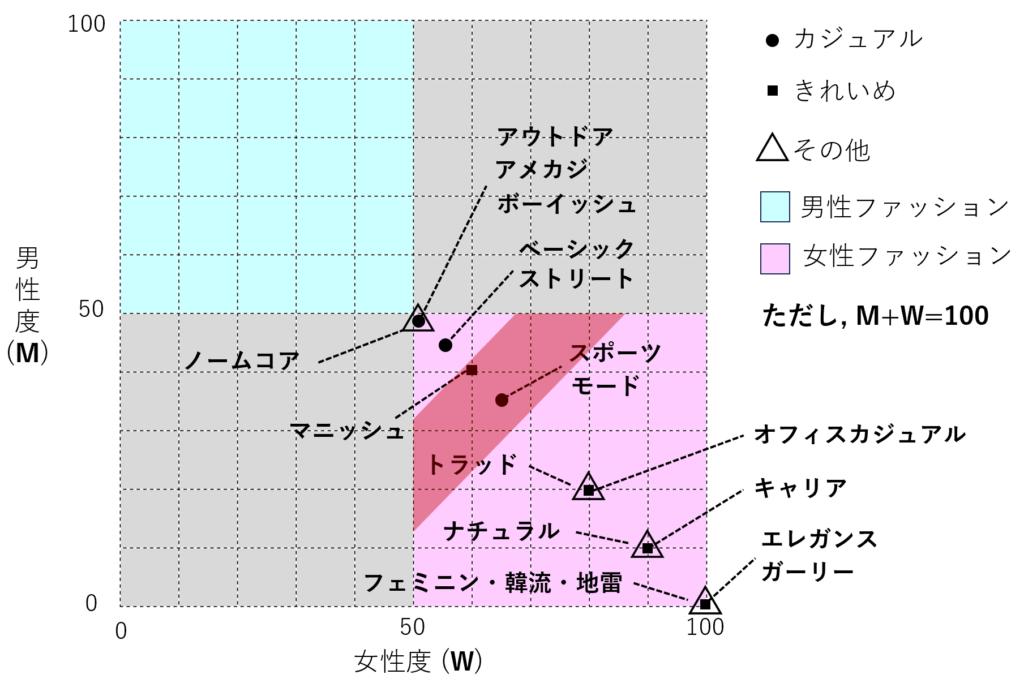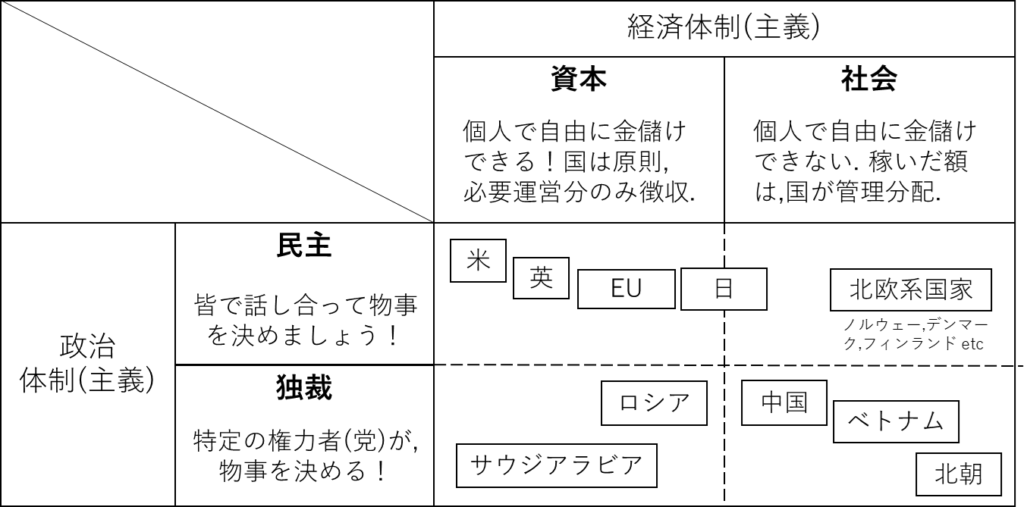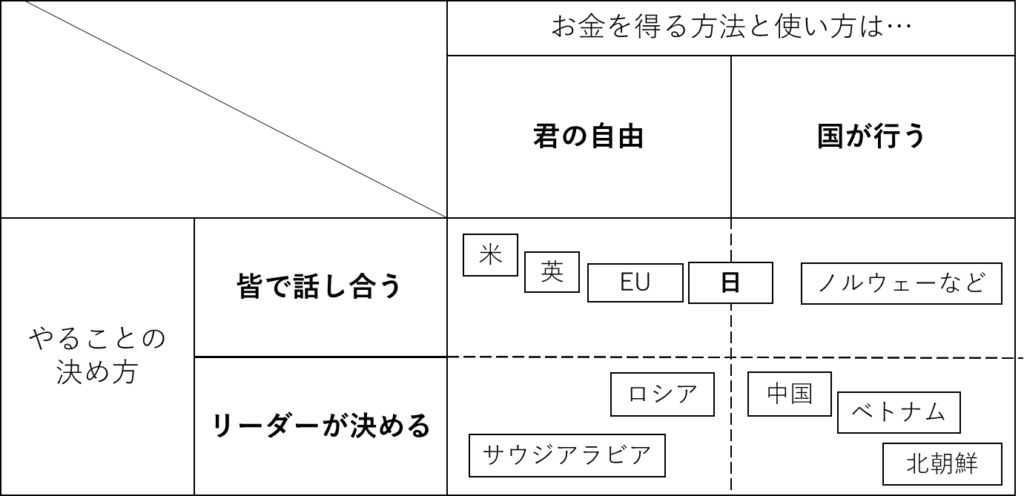最近、日本の会社で、変な風潮が増えている。
それは、「業務よりもプライベートを優先してOK」という考え方である。会社の役員がそうしてください!と社内報で告知しているところもあるようである。
私は、この考えには大反対である。こんなことを組織の皆がやっていたら、まじめに働く人がいなくなってしまうからである。多くの仕事は、チームプレイである。日程、お金、人が決まっている。そうした中で、ある人が一方的に「明日から家族旅行なので10日間休みます。よろしく!」と言ったら、業務が停止してしまうであろう。停止とはいかなくても、その業務をやらざるを得なくなった社員に業務負荷が集中するので、その人は主業務の余力でそれを処理しようとしたり、慣れない仕事をしなければならなかったりすることになるので、成果は大きく低下するであろう。加えて、埋め合わせをすることになった社員は、心身を疲弊するので、健康を害する可能性が高くなる。仮に、埋め合わせ分の報酬をもらえたとしてもそれはカンフル剤のようなもので、長期的には通用しない方法である。顕在意識は「金」で満たされていても、自由と休息を求める潜在意識と、それに連動した体が疲弊する一方なので、緊張の糸が切れたときに体が動かなくなってしまうからである。こうなったら、数か月まともに働くことはできない。
この話は、何も絵空事ではない。容易にそうなることが想像できる最悪なシナリオである。ばかげている。しかし、徐々に増えているのである。あなたが会社員ならば、自分の周りや、あなた自身に問うてほしい。一方的に、「明日休みます。」とか、「ひと月前からここに会議が入っているのは知っていましたが、明日家族行事なので休みます。」とか言っていませんか? 私は、それは極めて利己的な、迷惑行為だと思います。そうでないという納得のいく理由があるとしたら、是非説明していただきたい。つまり、あなたが一方的に空けた穴を、どの従業員にも請け負わせることなく埋める方法を説明していただきたい。
話は少し変わる。組織は、ある期限内に達成するべき目標が必ずある。そこで働く従業員は、その目標のために組織に採用されているのである。そして、目標達成のための貢献の対価として給料を与えられてのである。これが、仕えるということである。立場は、組織が上で従業員は下である。この関係が崩れると、仕事は成立しない。立場の弱い組織が、立場が上の従業員に命令( いや、お願い )を出したとして、それを受け取った従業員は「めんどくさい。やらない。」となるのは明白である。そうしないと利益がでないよ!と脅しても、組織にある程度の従業員がいれば、誰かがやるだろう…という意識が働き、組織の生産性は枯渇するのである。はじめは誰かがやるかもしれないが、やってあげた成果が平均化されることに気が付き、その人もやらなくなるであろう。体を壊す前に辞めるであろう。だから、立場は組織が上で、従業員は下なのである。そして、組織に勤めている以上は、「業務はプライベートより優先」が原則であり、「業務よりもプライベート優先で!」などという考えは、持ち込んではならないのである。それは、組織を崩壊させる悪魔の囁きのようなものである。
ここで、「そうはいっても、そうした仕組みに助けられた」という人が手を挙げるであろう。例えば、育休・産休・介護・長期療養、そして家族サービスなど。いずれも大切なことである。しかし、これらの休みを取った方は、休み中に労働利益を上げていないのだから対価しての給料がないのが原則であることを忘れてはならない。有給制度は権利とか思っているのは、偏った思い込みである。「何もしなければ、何も生まれない」という万物の基本を思い起こせば、少しは考えが改まるのではないだろうか?
では、有給休暇を胸を張って習得するにはどうしたらよいか?私は、下記を提言する。
1.有給休暇日数分の価値がある成果を蓄えてから休む
2.あなたの業務の代役を探し、その人にあなたが一部労働対価を払う
2-1. 利己的な突然の休暇の場合は、あなたの日給分を代役メンバーに支払う。
2-2. 育休・産休・介護・療養等の場合は、あなたの給与の1割を同様に支払う。
ただし、あなたの業務を主業務として担当する代役が事前に見つかっている場合は、この限りではない。
当たり前のことを言っているつもりである。1は、「やることはやって、そこで生まれた余裕分を休暇にあてましょう」ということである。例えば、一日で3日分の労働成果を上げられたら、その分休むとか。また、労働をポイント制にしてもよいと思う。日々の労働で他人の労働を救済し、互いに合意できたらポイントを習得する。それがある基準を超えたら、誰に憚ることなく休めるとか。この場合は、いきなり休むとチームが困るじゃないか!という議論が再燃するであろう。その理由は、埋め合わせをするために成果が落ちるし、それをやった者が疲労するからであろう。しかし、その場合の休んだ人によって組織の日々の労働成果が高められており、その恩恵をみんなが受けているのならば、お相子とはいえないであろうか( ご自身でも一度考えてみてほしい )。もしこのポイント制がよいならば、有給習得理由として「ポイント消化のため」と堂々とかける。ちなみに、日々の業務チームとは違う、外部研修とか、特別プロジェクトとかでの休みは、いかなる理由であれ理解されないので注意が必要である。2は、結局カンフル剤としての金で埋め合わせをするという方法である。今は、これすらもないところが殆どなので、「休んだもの勝」な現状がある。真面目な人が損をしないように、「休んだら代役にお礼をする」という当たり前の行動を仕組化するという主張である。お礼として何が良いか?と考えたとき、結局、お金が最も単純で強力と考えたので、お金とした。
以上、今日も長々と述べてきた。本日の主張をまとめると下記である。
・最近、「業務よりもプライベート優先」という論調がある。
・私は、この論は、おかしいと考える。
・理由は、チームプレイが成立しないから。
代役の人が疲れ、成果が落ち、業績は低下。組織の形態が成立しない。
・有給をとる際の、有給習得者が満たすべき最低条件の提言。
1.やるべきことやり溜めて、その分を休む
2.代役を立て、その人に労働対価を支払う
変わりゆく労働形態と労働環境。一見、合理的に見えて、悪魔の仕組みが沢山あります。その仕組みを活用する人は「利己的で、組織や社会のことを機械的に割り切るような、その他多数の人」です。「本当に優秀で真面目で、真に組織や社会のことを考え主体的に提案し、実際に組織を支えているような少数派の人」は、こうした仕組みの犠牲者となっていることを忘れてはなりません。