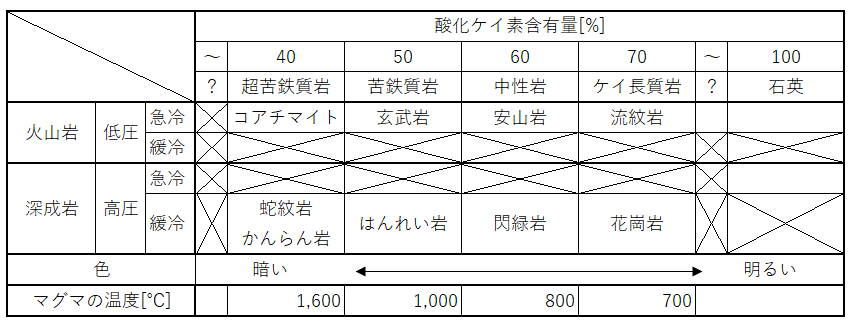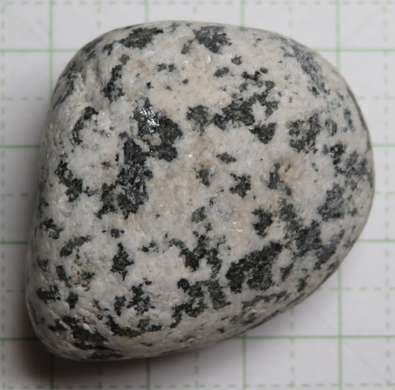本日は、マイペースであることについて、述べたいと思う。
① 電車の中で、他人への立ち位置や音など気にせず、自分のゲームや動画鑑賞に没頭する人。
② マフラーを改造して、爆音を立てて公道を走る車やバイク。
③ 職場で、連携した仕事が必要なのに、自分の職域を勝手に制限し、そこだけ完了したらそれで終わりという人。
④ 恋活や婚活をしているのに、自分はマイペースなので一生一人でもよい。良い人がいればいいな程度の人。
⑤ 家の中で与えられた仕事をして金を稼ぎ、ゲームなどの趣味に没頭し、それだけで人生十分とする人。
⑥ 公共の場ではマスクをして、飲食は極力控える。食べても、ガムや飴くらいにする。その上で、本を読んだりする。
これらは、皆、マイペースであることの例である。
マイペースであることは、一見すると、別に悪いことではない。なぜなら、マイペースであるためには、自分がありたい姿、つまり、「軸」があるということだからだ。軸があるということは、それは、自立した人間であることを意味する。だが、自分がありたい姿を描くことは、子供でもできる。社会的責任を負った大人は、この程度のマイペースではいけないのである。「一見すると」と言う具合に、含みを持たせたのは、その為である。
では、大人はどんなマイペースでなければならないのか? 大人は、子供と違い、責任を負う立場にある。何故責任が問われるかといえば、そうしないと社会の秩序が乱れるからである。社会の秩序とは、突き詰めると、人と人との連携・協力・調和のことである。調和は、互いに思いやる姿勢によって初めて成立する。従って、人との調和が成立する個人のマイペースとは、「相手への思いやりを第一に考えた、マイペース」と言うことである。つまり、「利他的なマイペース」が、大人のマイペースということなのである。
では、この利他的なマイペースの視点で、①~⑥を見てみよう。
①は、他人の快適さを考えていないので、利他的なマイペースではない。よって、これをやっている人は、子供である。
②は、爆音を立てている時点で、他人への配慮がない。よって、利他的なマイペースではないので、子供である。
③は、自分の職域の勝手な制限をしている時点で、もはや配慮が欠如している。その職務で十分なことの合意をとれていないので、この人は、他人への配慮がない。よって、利他的なマイペースではない、子供である。
④は、互いに調和できる人を探す行動をしているに、自分は一人でも充実しているので相手は特に必要ないと言っている。こういう主張をする人は、「子供である自分を、ありのままに居させてくれる人」としか結ばれないであろう。なぜなら、「協力しよう!」と言っているのに、「私は協力する必要がないが、あなたが必要と言うから居てあげる」という関係だからだ。さらに、こうした人は、「良い人がいたら」とも言っている。この良い人というのは、考える限り2パターンしかない。一つは、「自分が夫婦やそれに伴う社会活動で非協力的だが、好き勝手させてくれる、大金持ち」。もう一つは、「自分が追いかけたくなるようなプリンス /プリンセス」である。そんな人は、あまり居ないと考えた方がよいことは、いわずもがなであろう。こういった人は、今後「利他的」な意識に変えていかないと、若さゆえに快適な一人の人生を突き進むことになるであろう。只のマイペースな子供だからだ。
⑤は、仕事という形で社会と関わっているので、利他的なマイペースである。仕事を依頼した人は、ちゃんと結果が返ってくれば安心するであろう。だから、この人は、大人である。
⑥は、他人を配慮した行動そのものである。マスクをするのは、他人からの感染を防ぐ効果と、他人へうつさない効果が期待できる。マスクをする行為と、それを公共の場で長時間続けようとする姿勢は、利他的である。よって、大人である。
以上、マイペースであることについて述べてきた。身体は大人になっても、只のマイペースの人は多いです。是非、利他的なマイペースを目指し、身体も心も魂も大人な人が多くなってくれることを願っています。
【本日の動画】オオバンの隊列
野生の生き物こそ、協調性が求められます。自然の前に、一人では生きていけないからです。人は、今一度、原始の在り方を学ばなくてはならないと思うのです。