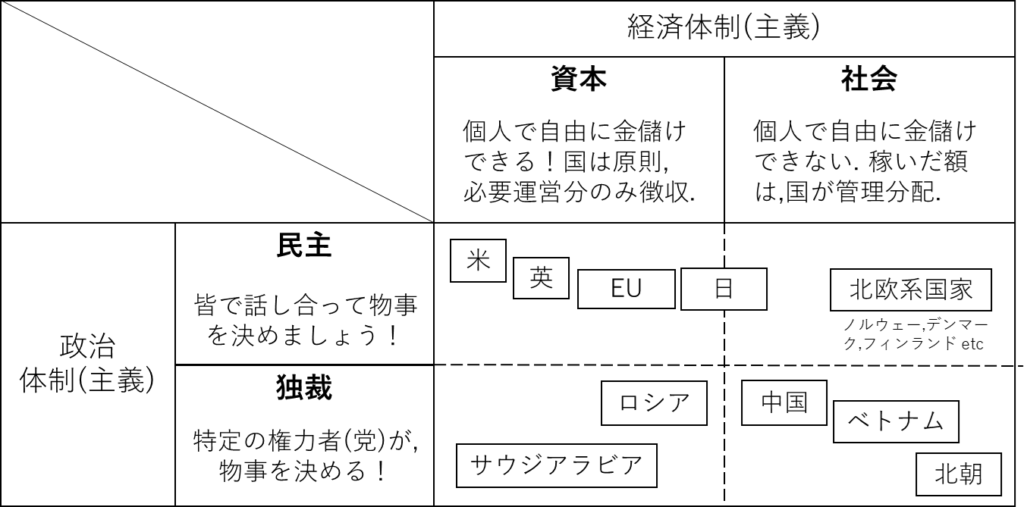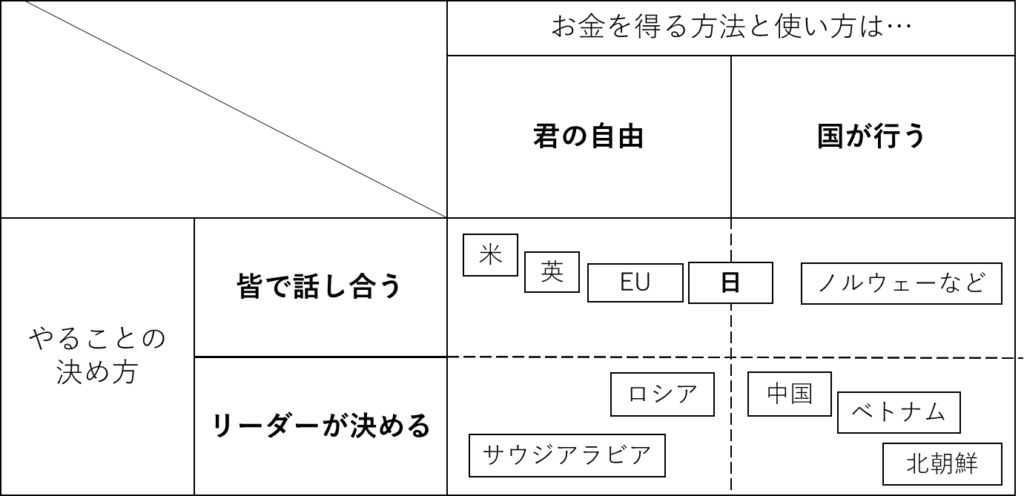これは私が小学生の高学年だったころの話です。
当時、私は小学校が終わると、直ぐに学習塾に通っていました。勉強は社会と国語以外は壊滅的に苦手で大嫌いでしたが、「行くものだ」という刷り込みによって毎日行っていました。
5時から9時までの授業。週末のテスト。週明けの順位発表。親や先生からの激しい叱責。
中学受験が終わるまで、この繰り返しでした。
このような生活をおくるうちに、私は大いに疲れてしまって、次第に日常的に神頼みをするようになりました。
普通に考えれば、たかが塾のテスト如きで神仏の力を求めるなどアホか。。と笑い話になるかもしれませんが、誰に何と言われようと、思考する頭がまだ生育の過程でできていない当時の私には、暗記で直接対処できない問題は解けず、従って点数は伸び悩み、それ以上を要求されても成す術がなかったのです。だから、神頼みしないと日々を乗り切れなかったのです。
こんなとき、同じ塾の仲間たちの中で流行っていたのは、シャープペンシルの収集でした。いや、かなり流行っていたと思います。週に二日は文具店(丸善)に行き、自分好みのペンを10分ほど探して、ときに100~300円くらいの品を買っていました(お小遣いをためて1000円てのもありました)。重くて重心が安定しているペン、1mmまで芯が使えるペン、製図ペン、ノック式、筐体側面にプッシュボタンがあるペン、捻ると芯が出るペン、キャップがあるペンetcその多様性に心躍らされたものです。
では、なぜ当時の私たちは、これほどペンに惹かれたのでしょうか?今思えば、それは、ペンにある種の神や力が宿っていると感じていたからだと思うのです。単に、感覚的に惹かれるからだけではありません。もしそれだけなら、何本も購入するとは考えられないからです。
皆さんもこんな経験はないでしょうか? 尊敬する人が所持している物を自分も手に入れて、頑張りたい!とか、神社で売っている合格鉛筆を買ってテストに使うとか。前者は、尊敬する人と同じ物を使うことで、その人のようなりたいと願う心理の表れと私は思うのです。それを示すように、重要なテストがあるたびに、優秀な子が使っているのと同じペンを買ってきて使う子が大勢いました。私は、神社の合格鉛筆の力がその断面形状や色にあるのではないかと思い、ペンの形に「答案を作成する閃きの力」が宿ると思い、色々な安物ペンを収集していました。1年で10本くらい( 1,500~3,000円くらいか… )
このようにして、合格鉛筆と色んなシャープペンシルを収集し、使い分けて、苦しい受験期の中に鑑賞する喜び、使う楽しさ、希望を見出していたのです。問題が解ける天才や秀才たちには、これとは別次元の悩みがあったでしょうが、平均±標準偏差 あたりの人は、何となくこんな経験があると思うのです。
まもなく子供たちは夏休みに入り、受験生は、遅れ挽回とさらなる成長に向けて重要な時期に入ります。毎年、この夏のうだるような蒸し暑さを感じたり、文具コーナーをウロウロするNバックを背負った子供を見かけたりするたびに、遠い日の、ペンに神が宿ると真剣に信じて問題と格闘していた弱い自分を思い出し、心の中で彼らを応援してしまうのです。